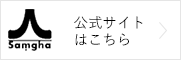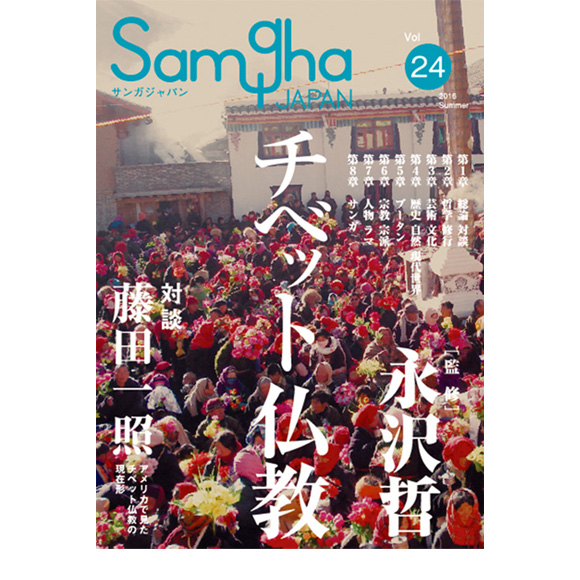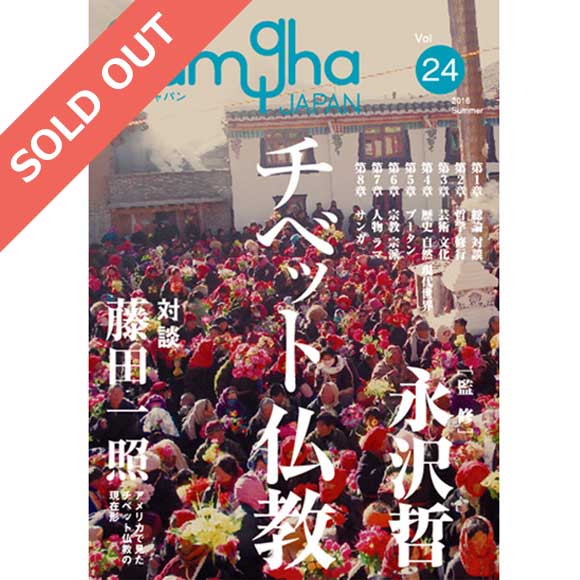【SOLD OUT】サンガジャパン Vol.24 (2016Summer)
通常価格:¥ 3,080 税込
¥ 3,080 税込
加算ポイント:28pt
商品コード: 300620
カバー痛みあり、在庫限り。ご了承ください。
発売日:2016年8月28日
監修:永沢哲
ISBN:9784865640625 C0015
A5判くるみ 本文764ページ
特集:チベット仏教
今、改めて概観する チベット仏教の現在 (編集部)
宗教学者の永澤哲氏の監修のもと、チベット仏教を一から知りなおし、今現在の様子を伝える、総特集。
ジョブズの禅や、医療・ビジネス分野におけるマインドフルネスに代表されるように、欧米での仏教の広がりと影響を知りつつある。
仏教は、同時代の新鮮な精神の潮流として捉えられているといってよいのではないだろうか。
武蔵野大学のケネス・タナカ教授は『目覚める宗教』(サンガ新書)のなかで、アメリカの仏教への入り口を瞑想を中心に見たときの系統をテーラワーダ、禅、チベットの三つ分類している。ダライ・ラマ14世の活躍はもちろん、チョギャム・トゥルンパなどを通して欧米に渡ったチベット仏教は、今現在の精神潮流に深く大きな影響を与えているのだ。
では、テーラワーダ仏教を知り、禅に親しむ私たちは、チベット仏教について何を知っているのか。改めて問うべき時期にきているはずである。
一時のブームから時を経て、今改めてチベット仏教の現在を、本書は概観する。
哲学から文学、修行の体系、文字の読み方、そして現在日本で活動するチベット仏教のサンガ(勉強や修行のグループ)の紹介にいたるまで、多岐にわたる内容を一冊に収録。チベット仏教の今がここにある。
序 文 (永沢哲)
チベットの行者の朝は早い。三時前に起き出すと、最初の一座をすわる。一座は三時間くらい。それから、ヒマラヤスギやヨモギの葉を燃やし、よい香りのする煙を、三宝や土地神、精霊たちに供養する。終わったら、朝食だ。乾いたヤクの糞で火をおこし、お茶を沸かす。ヤクは、標高三千メートル以上の高地で、風雪に耐えて成長する高山植物や薬草を食べて育つ。白い煙は、とても心地よい香りがする。瞑想の修習は、一日に四座。あいまに勤行をし、お経を読み、食事を作る。就寝は、たいがい九時半を回る。
僧院で、学問をする僧侶たちの生活も、あまり変わらない。夜明け前に起き出すと、帰依と懺悔の言葉を唱えながら、裸足で五体投地の礼拝をくり返す。東の空が白みはじめると、本堂に集まって朝の勤行をし、朝食をとる。経典の学習と暗記は、夜遅くまで続く。
こうしたルーティンは、チベットにインドの仏教が本格的に移植されはじめた八世紀から現在まで。ほぼ変わらずに保たれてきた。仏教には、仏典の学問と修習による悟りという二つの柱がある。そんなふうに考えるインド仏教の伝統に、チベット人たちは、たいそう忠実であろうとしてきたのである。
八世紀に新しく創られたサムイェの僧院では、インドや中国からはるばるやって来た学僧や禅僧たちが、チベット人の訳経僧たちと問答を重ねながら、厖大な量の経典の翻訳作業にいそしんだ。一方、サムイェから五、六時間歩いたチムプ―やヤマルンに新しく開かれた行場では、ごつごつした岩山の急な斜面に散在する洞窟の中で、新しくチベット語に訳された経典をもとに、密教の瞑想修行を続けられた。
インドからの新しい仏典や瞑想技法の導入は、ほぼ十三世紀までつづいた。インドにおいて二千年近くにわたって育まれ、成長した顕教、密教の哲学や瞑想技法、因明(論理学)などの知恵の伝統は、白い雪の冠をかぶった神々の山に囲まれ、深い青に澄みわたった天空に近く生きるチベット人の精神の大地に移植され、大きく開花した。
この本は、そうしたチベットの仏教のエッセンスを取りだすことをめざしている。
ブッダの教えは、難解な仏典を学ぶ学僧や、一生瞑想修行に打ち込む行者たちだけのものではなかった。絵や音楽、踊り、物語、オペラ劇といった芸術の様式をつうじて、チベット人の心に深く根を下ろしてきた。
それだけではない。二十世紀になって、欲望によってつき動かされる資本主義とテクノロジーに覆われた世界と、本格的に接触するようになった、チベット人やブータン人たちは、仏教の深々とした伝統を土台にしながら、新しい科学と対話し、人類が直面する問題を乗り越えていくためのヴィジョンを、提示しようとしてきた。あるいは、映画をはじめとするポップ・カルチャーをつうじて、現代を生きるじぶんたちの感覚を表現してきた。
本書は、その全体を描き出そうとする、ささやかな試みである。
目次
特集 チベット仏教
- 序 永沢哲
- 対談:アメリカで見たチベット仏教の現在形 永沢哲×藤田一照
- チベット仏教の高僧が語る チベット仏教と文化の生きた姿ーニチャン・リンポチェ インタビュー 【聞き手】永沢哲
- チベット仏教概説 永沢哲
- 地図
- 用語解説
- インドからチベットへの中観派の展開 熊谷誠慈
- ツォンカパの中観思想 福田洋一
- サキャ派の中観見解について クンガ・テンパ
- 他空説ー相対的な世界は、それ自体において空である(自空)。絶対的な真理は、それ以外が空である(他空) 永沢哲
- 具足戒、大乗戒、三昧耶戒ークレイジー・ウィズダムと呼ばれたケンポ・カンシャルのお添えを通して知る、仏教のサバイバル 永沢哲
- ラムリムとガクリム 齋藤保高
- 「解脱の道」マハームドラーと、「方便の道」ナーローパの六法ー身体技法=ナーローパの六法/解脱に導く道=マハームドーラ 永沢哲
- ゾクチェンとは何か-チベット密教を代表するプラクティス「ゾクチェン」のアウトライン 永沢哲
- チベット密教は仏教なのか?-その哲学的な成熟の中に貫かれている仏教の本質を整理する 永沢哲
- 顕教の瞑想ー菩提心の習得と菩薩行- 永沢哲
- ロジョンとその後世への影響 井内真帆
- ダライ・ラマ十四世の世俗倫理と非暴力思想 辻村優英
- チュー:「我執を断つ」-悪霊に身体を布施する修行の体系 永沢哲
- ラムリムとガクリム 齋藤保高
- 長寿の修行ーチベット医学にもとづく瞑想・健康・長寿 永沢哲
- チベットの死の教えーフィールドワークから 永沢哲
中有 において、恐怖から救う祈り(『シトー・ゴンパ・ランドル』から) 永沢哲- 新連載 光の中の哲学:第一部 虹の身体(1) 永沢哲
- 現代の虹の身体ー2015年3月8日、虹の身体になったチメ・リグジン・リンポチェ 箱寺孝彦
- 骨の宝石-ブッダの境地の明石ー五色に輝く仏舎利 永沢哲
- ボン教の教えの継承ー八世紀から続くボン教のゾクチェンー『シャンシュン・ニェンギュ』の教え 箱寺孝彦
- 仏子の三十七の修行(rgyal sras lag len so bdum ma)-ブッダの息子のための大乗仏教の修行のエッセンス 【作】ギュルセ・トクメ・サンポ 【訳・解説】永沢哲
- チベット仏教とチベットを知るブックガイド 三浦順子
- チベット文学案内ー仏教の価値観が深く心に生きるチベットの精神世界。時代が移り状況が変動する中で息づく、チベット文学世界の伝統と新たなる息吹 三浦順子
- チベット映画クロニクル 長田幸康
- 瞑想と仏画ータンカ(仏画)と導かれた、ゲンラ(先生)との日々 デゥプイ操
- チャムとガルー仏教瞑想とダンス-伝統の踊りと現代に想像される新たなヴィジョンの密教のダンス宗教人類学者 永沢哲
- 物語・宗教歌・説法ー道しるべとなったもの 三宅伸一郎
- 自然への負債をあがなう民衆の儀礼ー微細で純粋な光のエレイメントで穢れを浄化するサンの儀礼 永沢哲
- 巡礼とボン教の山神ー衆生の救済を願い、「めぐり、あるく」巡礼の現在 小西賢吾
- チベット医学と仏教ープラーナに精通し、アーユルヴェーダに基礎づけられ、仏教から占星術までが統合された医学とは何か 永沢哲
- チベット文学を読むーチベット大蔵経典の深みに行くなら、避けて通れないチベット文学を簡単解説。ローマ字表記の方法ワイリー式も理解する。 星泉
- チベットのお経の話 佐藤剛裕
- 歴史に観るチベット仏教の特徴 永沢哲
- パンチェン・ラマから捉えるチベットの歴史ーダライ・ラマからと互いに転生者を認定しあうラマの歴史と現行 長田幸康
- チベット仏教の世界への広がり概説 永沢哲
- ダライラマ十四世の経済・社会思想 辻村優英
- 世界を相手に菩薩道を説くダライ・ラマ十四世 石濱裕美子
- サキャ派の海外への広がり クンガ・テンパ
- 苦難を乗り越えた世界に広がるボン教ー展開する三つのグループ 箱寺孝彦
- 浄土としてのチベットー神々と人間が交歓するアニミズム大地と仏国土 永沢哲
- 中世チベットの偉大な
諷狂行者 国土を改良し多くの詩作をのこしたタントル・ギュルポの生涯 永沢哲 - ボン教の自然観ー人間中心主義的な価値観を揺さぶる人間と自然の交渉する領域 小西賢吾
- ブータンの国民総幸福(GNH)の政策:真の幸福とは何かー仏教的な価値観に基づくオルタナティブな世界への試み 上田晶子
- ブータンの仏教教育と国民総幸福(GNH)の政策-対伝来のマインドフルネスを教育現場で実践する仏教国の試み 永沢哲
- パドマサンバヴァとブータンー歴史的事実を超えた聖なる存在 安田章紀
- ペパリンマ伝ーブータンの人々の心に生きる国民的聖人 安田章紀
- ニンマ派概説 永沢哲
- ニンマ派の代表的な祖師 永沢哲
- カギュ派概説 吉村均
- カギュ派の代表的な祖師 吉村均
- サキャ派概説 クンガ・テンパ
- カダム派概説 井内真帆
- カダム派の代表的な祖師 井内真帆
- ゲルク派概説 齋藤保高
- ゲルク派の代表的な祖師 長田幸康/齋藤保高
- その他の系譜 永沢哲
- ボン教と仏教-太古の教えとアジア各地の修行の伝統が出会い織り成す体系化へのダイナミズム 永沢哲
- チベット人の生贄をやめさせたのは誰か?-ボン教のユニークネス
- チベット仏教におけるリメ(無遍)のアプローチー歴史、哲学、文化保存ー マルク=ヘンリ・デロッシュ
- シュクセプ・ジェツンマ/ジグテル・イェシェ・ドルジェ/ディルゴ・ケンツェ/チャダル・サンギュ・ドルジェ/ドドゥプチェン・ジグメ・ティンレー・パルワル/ペマ・ノルブ・リンポチェ/ケンポ・ジグメ・プンツォク/チューギェル・ナムカイ・ノルブ/ソギャル・リンポチェ/ナムケーニンポ・リンポチェ
- カルマパ・ランジュン・リクペ・ドルジェ/ジェ・ゲンドゥン・リンチェン/ディクン・キャムグン・rチェツァン七世/ドゥクチェン・リンポチェ十二世/ヨンゲー・ミンギュル/チョギャム・トゥルンパ
- ゾンサル・ジャムヤン・ケンツェ・ワンポ/ジャムヤン・ロテル・ワンポ/ジャムヤン・ケンツェ・チューキ・ルドゥ/サキャ・ティジン/ゾンサル・ジャムヤン・ケンツェ
- ガンデン・ティパ・ロプサン・ニマ/ダライ・ラマ十四世テンジン・ギャツォ
- ワンドゥ・リンポチェ
- ヨンズィン・ロポン・テンズィン・ナムダク・リンポチェ
- ゾクチェン・コミュニティ・ジャパン/ムンセルリン
- チベット仏教普及協会(ポラタ・カレッジ)
- マンガラ・シュリ・ブティ・ジャパン
- 東京ゾクチェンセンター
- 小さな瞑想教室
- シッダールタズ・インテント・ジャパン
- 日本にチベット仏教を定着させた二つの団体(チベット文化研究会とダライ・ラマ法王日本代表部事務所)
第1章 総論 対談
第2章 哲学 修行
第3章 芸術 文化
第4章 歴史 自然 現代世界
第5章 ブータン
第6章 ブータン
第7章 人物 ラマ
ニンマ派
カギュ派
サキャ派
ゲルク派
シチェ派、ニンマ派
ボン教
その他
第8章 サンガ
特集あとがき
連載第八回 日本仏教は仏教なのか? 藤本晃
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆