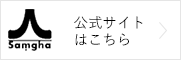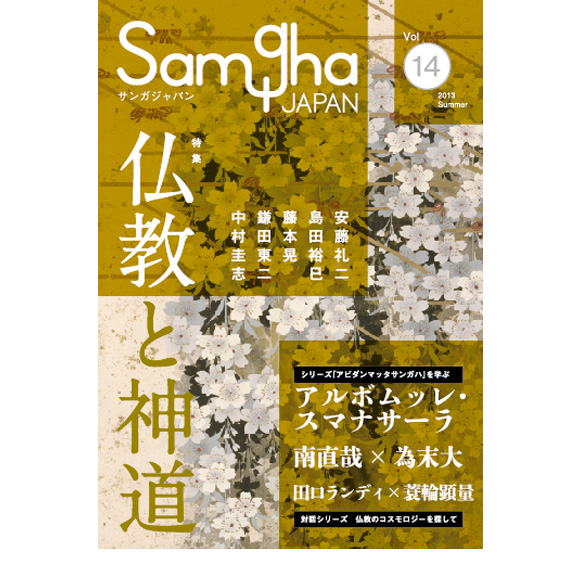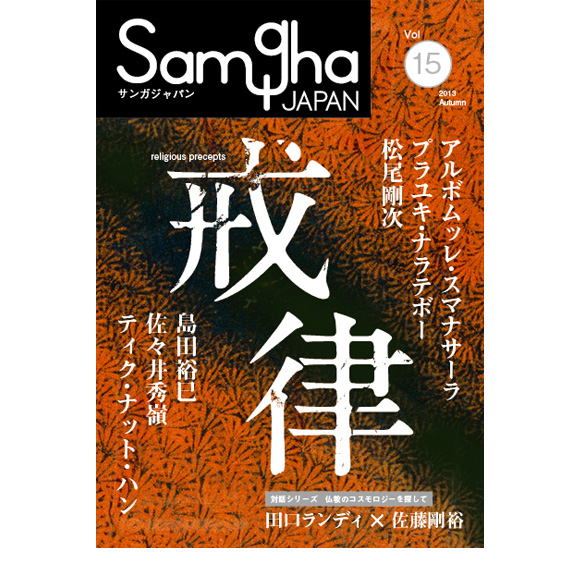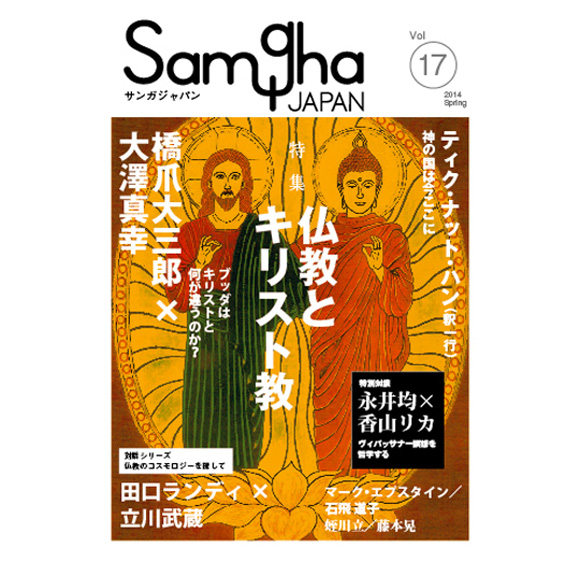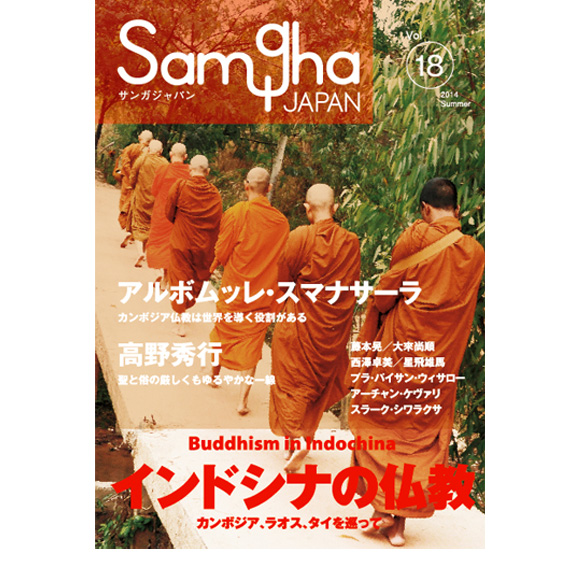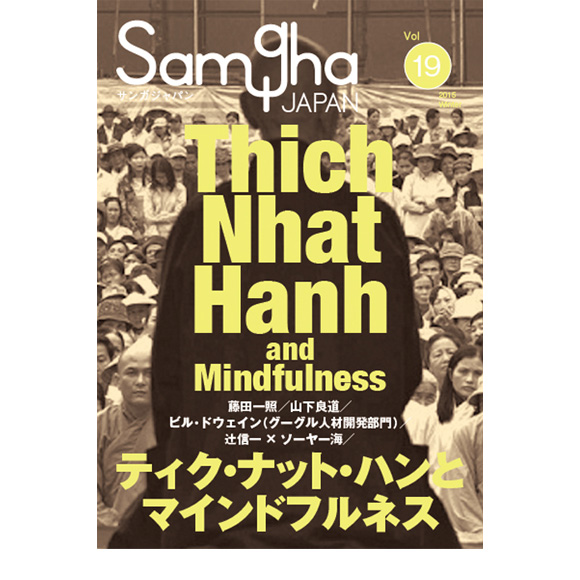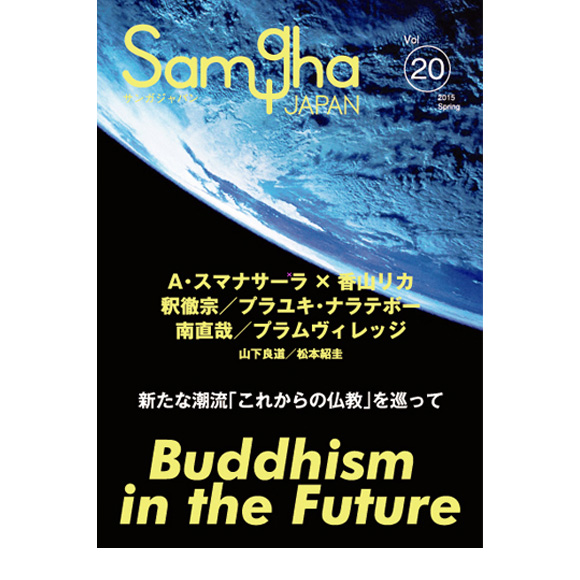サンガジャパンVol.14(2013Summer)
通常価格:¥ 1,980 税込
¥ 1,980 税込
加算ポイント:18pt
商品コード: 200520
発売日:2013年6月27日
寄稿:安藤礼二・島田裕巳,藤本晃,鎌田東二,中村圭志,アルボムッレ・スマナサーラ,南直哉×為末大,田口ランディ×蓑輪顕量
ISBN:9784905425526 C0015
A5判くるみ
特集:仏教と神道
2013年の今年、伊勢神宮は62回目の式年遷宮を迎える。伊勢神宮の式年遷宮は20年に一度行われ、それだけでも久しぶりのことであるが、それに加えて本年は60年に一度の出雲大社の遷宮も行われる。そのような意味で、本年は神道にとって近来稀な年といえるだろう。そのような年にあたって、『サンガジャパン』で通常主題として扱っている仏教と、神道との関わりについて再考してみようと思い、今回の特集を企画した。 神道というものを理解するにあたって、まずは世界史的視点から宗教というものを捉えなおしているのが中村圭志氏の「神道 東ユーラシア多神教世界からの展望」だ。中村氏は世界宗教をまず、多神教と一神教に分別する。厳しい風土条件や戦乱に苛まれた西ユーラシア世界では、神々も厳しいサバイバル戦を強いられ、敗者の神々たちは忘れさられてきた傾向にあるという。その一方、東ユーラシア大陸では、勝者の神々が打ち立てられた後にも、文化的風土の違いから敗者の神々もまた併存するという状況があった。これが、日本の神道と仏教に見られる「習合」というユニークな概念の原形となったのではないかというのである。 この神仏習合というものを考える際に極めて重要となる存在が「権現」である。島田裕巳氏の「権現とは何か」は、権現という存在を神道と仏教をつなぐものとして考察した論考である。「仏が衆生を救うために種々の姿をとってに現れたもの」として権現を理解することが、神仏習合を理解することに通じるとする。そして、この神仏習合について理解することこそが、日本宗教史の基本中の基本を理解することにつながると島田氏は説くのである。 仏が化身して日本の神として現れたとする、いわゆる本地垂迹説を前提とする神道論から、こうした神道、ひいては日本の伝統文化は仏教が産み育てたものであると、藤本晃師は「仏教が、日本と神道を産み育てた」の中で主張をする。そして、律令国家としての日本を成立させるために大陸から輸入された仏教は、紆余曲折を経て日本人の心に根を下ろし、日本の精神文化を発展させる礎となったといわれる。こうして日本人の心の基盤となった仏教は、明治以降の神仏分離、廃仏毀釈、そして戦後における宗教の世俗化といった時代の荒波にも負けず、堂々たる存在感を現代にも示しているというのである。大変説得力のある議論だといえよう。 さらに、教義体系として日本文化の基層をなすようになった仏教とは対照的に、芸術・芸能といった感覚的な側面から潜在的に日本人の心を支えてきたのが神道であると鎌田東二氏は主張をする。そして、神道を理解するには仏教のように経典を繙くのではなく、歌(詩)などの芸術的な側面から理解することが必要なのであるという鎌田氏による「神道と浄め」は、神道を深く理解するためのヒントが多くつまった刺激的な論考だ。 その他にも、安藤礼二氏による折口信夫論など、必読の記事から本特集は成っている。本特集が、日本文化における仏教と神道の新たなる架け橋の一つとなれるのなら、幸いである。(編集部)
目次
特集 仏教と神道
- 執筆者一覧
- 編集後記
神道と浄め 鎌田東二
権現とは何か 島田裕巳
折口信夫を通して見る神仏習合と神懸かりの系譜 安藤礼二
仏教が、日本の神道を生み育てた 藤本晃
シリーズ『アビダンマッタンサンガハ』を学ぶ(3) 「三解脱」と「七つの清浄(1)(戒清浄・心清浄)」 アルボムッレ・スマナサーラ
田口ランディ対話シリーズ 仏教のコスモロジーを探して-仏教の瞑想と、体験の伝承 第四回:蓑輪顕量
対談 求道者ふたり、本質を語る。 南直哉×為末大
般若心経は間違いではない? 石飛道子
連載第十三回 パーリ三蔵読破への道-『セデック・バレ』と『戦士経』―「首狩り宗教」から魂を解き放つー 佐藤哲郎
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆