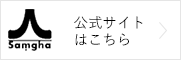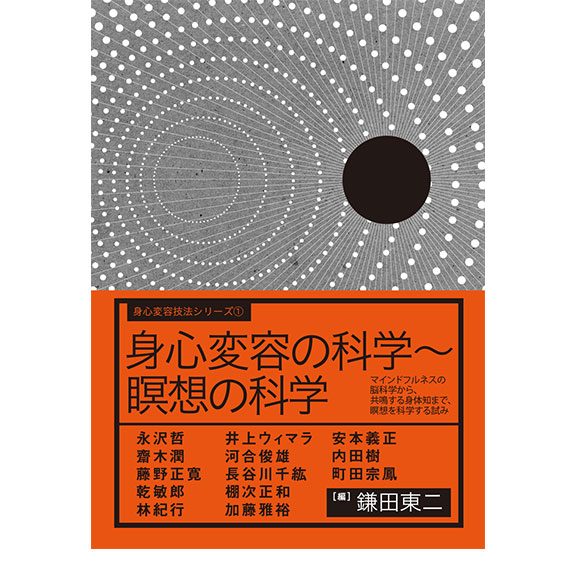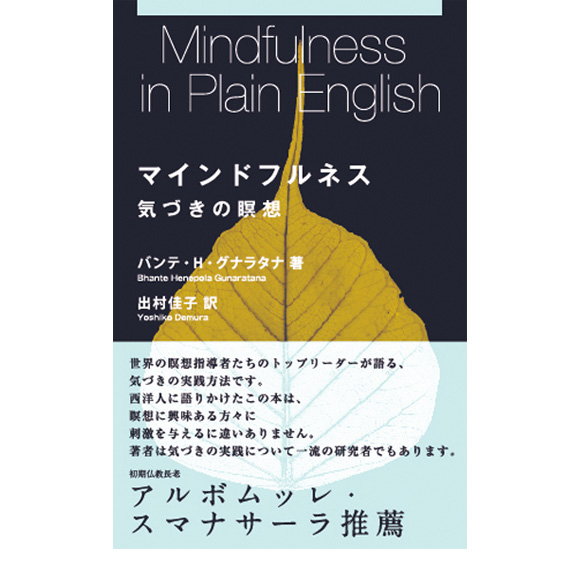身心変容の科学~瞑想の科学
目次
序文 鎌田東二(研究代表者/京都大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所特任教授)
1 身心変容技法研究の始まりとその時代的背景
2 心と脳をめぐる理論研究と実践研究としての身心変容技法研究
3 脳死体験と脳科学
4 「身心変容技法」研究のプランのいくつか
おわりに
第1部 瞑想の脳科学
- 4-1 「自己変容」のパラダイム
- 4-2 瞑想と自己変容の脳科学
- 4-3 慈悲の瞑想
- 4-4 マインドフルネス瞑想
- 6-1 トゥクタムと死の光明
- 6-2 仏舎利と「虹の身体」
第1章 瞑想の脳科学の現在
二十一世紀の瞑想する脳科学-自己変容のバランス 永沢哲(京都文教大学准教授/宗教学(チベット仏教)
1 Contemplative Neuroscience
2 心と生命研究所
3 「神経化学的自己」から「自己変容」へ
4 瞑想と自己変容の脳科学
5 タントラ、微細身、脳科学
6 脳科学を超えて-死の光明、仏舎利、虹の身体-
7 おわりに
第2章 瞑想を測定する
- 背景:瞑想の認知神経科学
- 仮説:瞑想は脳の自己組織化臨界性を高める
- 方法の概略:瞑想時の脳波測定実験
- おわりに
- 仮説:瞑想は脳の自己組織化臨界性を高める
- 方法 実験参加者/装置/手続き/解析
- 結果
- 考察
- 瞑想の認知神経科学
- おわりに
- 1-1 一人称の体験の基づいた三人称の科学
- 1-2 ゴエンカ式ヴィパッサナー瞑想
- 1-3 10日間コースの概要
- 1-4 コースにおける一人称的な体験から生じた問い
- 1-5 日常生活の置ける一人称的な体験を実験デザインに活かす
- 1-6 一人称の体験の基づいた三人称の科学への挑戦
瞑想と「協調による制御」:試論 齋木潤(京都大学大学院人間・環境学研究科教授/認知科学)
瞑想と注意
注意の認知神経科学:biased competition
バイアス競合モデルの拡張:default mode network
Effortless attentionという視点
瞑想の認知神経科学
「協調による制御」の達成
おわりに
瞑想は脳のネットワーク特性をどう変えるのか-脳波測定に向けての序論 齋木潤(京都大学大学院人間・環境学研究科教授/認知科学)
複雑ネットワークとしての脳
スケールフリー性とは何か
脳活動の時間ダイナミクスにおけるスケールフリー性
システムの時間ダイナミクスは相互作用の様式を反映する
脳波の時間ダイナミクスのスケールフリー性
LRTCを脳活動の指標として用いる
瞑想時の脳活動の時間ダイナミクス-LRTCに着目した解析
マインドフルネス瞑想と脳のシステム特性-脳波測定による検討 齋木潤(京都大学大学院人間・環境学研究科教授/認知科学)
マインドフルネス瞑想
脳のシステム特性:デフォルトモードネットワークと長範囲時間相関(LRTC)
デフォルトモードネットワーク(DMN)
脳波の長範囲時間相関
瞑想時の脳活動の時間ダイナミクス-LRTCに着目した解析
瞑想の神経科学研究-一人称の体験の基づいた三人称の科学 藤野正寛(京都大学大学院教育学研究科 博士後期過程二回生)
1 はじめに
2 実験序論
3 実験方法
4 実験結果
5 実験考察
6 実験結論
7 おわりに
第3章 瞑想の脳内メカニズム解明の試み
- 3-1 これまでに提案された催眠の基本仮説
- 3-2 離断と抑制
- 3-3 前頭葉の働き
- 4-1 機能的結合度
- 4-2 活動度
- 1-1 内側前頭葉前野の機能
- 1-2 TPJと楔前部の機能
- 2-1 CENと前帯状皮質の機能
- 2-2 感情とは予測信号である
- 3-1 背外側前頭前野
- 3-2 前帯状皮質
- 3-3 楔前部
- 5-1 予測符号化と自由エネルギー原理
- 5-2 感情の分類と構造
- 5-3 感情生成モデル
- 5-4 後部帯状皮質の重要性
- 5-5 催眠と瞑想の統一理論
身心変容の脳内メカニズム 乾敏郎(京都大学名誉教授。追手門学院大学心理学部教授/認知神経科学)
1 身体運動の予測に関する脳内メカニズム
2 自己認識の脳内メカニズム
3 幻覚と催眠
身体的自己と他者理解を可能にする神経機構 乾敏郎(京都大学名誉教授。追手門学院大学心理学部教授/認知神経科学)
1 身体的自己、時間知覚と島
2 島を中心とした結合
3 自己から他者理解へ
4 自己主体間と予測
5 他者を理解する二つのシステム
6 like-me システムの神経基盤
7 different-from-me システムの神経基盤
8 like-meシステムとdifferent-from-meシステムの相互作用
催眠と瞑想の脳内機構 乾敏郎(京都大学名誉教授。追手門学院大学心理学部教授/認知神経科学)
1 脳の三大ネットワーク(CEN、DMN、SN)-構成と機能と相互作用
2 円滑なコミュニケーションを遂行するために重要な三つのシステム
3 催眠による脳内ネットワークの変化
4 瞑想による脳内ネットワークの変化
5 統一理論を目指して
自由エネルギー原理に基づく催眠と瞑想の統一理論 乾敏郎(京都大学名誉教授。追手門学院大学心理学部教授/認知神経科学)
1 デフォルトモードネットワーク(DMN)の機能
2 中央実行ネットワーク(CEN)と顕著性ネットワーク(SN)の機能
3 催眠による活動変化
4 瞑想による脳内ネットワークの変化
5 統一理論
第4章 瞑想による身心変容の科学的実践研究の試み
- 2-1 ゴエンカ式瞑想法の歴史 ヴェン・レーディ・サヤドー/サヤ・テッジー/サヤジ・ウ・バ・キン/サティヤ・ナランヤ・ゴエンカ
- 2-2 ゴエンカ式ヴィパッサナー瞑想の特徴
- 2-3 ゴエンカ式瞑想法のコース概要 参加者に求められる規律/瞑想の種類/コースの種類
- 3-1 前提
- 3-2 心のプロセスと苦
- 3-3 身体感覚の重要性
- 3-4 集中瞑想のプロセス
- 3-5 洞察瞑想のプロセス
- 3-6 条件反応の消去
- 3-7 心の浄化
- 1-1 次第説法というアプローチ
- 1-2 四聖諦
- 1-3 解脱への入り口
- 1-4 解脱の条件とそれがもたらすもの
- 2-1 マインドフルネスとヴィパッサナー瞑想
- 2-2 ヴィパッサナー瞑想の基本
- 2-3 縁起の観察
- 2-4 私の階層性と意識の微分体験
- 2-5 関係性と自己概念
- 3-1 スピリチュアリティと家族の問題
- 3-2 人生で大切な五つの仕事
- 3-3 ほどよい母親的環境と注意研究
- 3-4 息遣いという次元
- 3-5 コンステレーション
- 3-6 子育てや出産におけるスピリチュアリティ
- ・クスリの服用に関して
- ・キーパーソンをほめる
- ・現実的な対処法を示す
- ・家族への自覚を促す
- ・その場での具体的な思いやり
身心変容の科学-マインドフルネスの科学 林紀行(ほうせんか病院心療内科医・緩和ケア病棟専任医)
1 はじめに
2 マインドフルネスのエビデンス
3 マインドフルネスと身心変容技法との関係性
4 まとめ
ニューロフィードバック-自身の脳活動による身心変容 齋木潤(京都大学大学院人間・環境学研究科教授/認知科学)
背景-マインドフルネス瞑想の科学的研究の現状と課題
ニューロフィードバック-瞑想理解のための新たな視点
ニューロフィードバックによって瞑想を理解するための課題
認知制御課題を用いた転移可能なニューロフィードバック手法の開発 進捗状況/今度の研究計画
おわりに
心のプロセスと瞑想のプロセスのモデル化の試み 藤野正寛(京都大学大学院教育学研究科 博士後期過程二回生)
1 はじめに
2 ゴエンカ式瞑想法の概要
3 心のプロセスとそれに対する瞑想のプロセスのモデル化
4 おわりに
研究構想:ヴィパッサナー瞑想、スピリチュアルケアから観た身心変容技法 井上ウィマラ(高野山大学文学部教授/スピリチュアルケア学・仏教瞑想研究)
1 瞑想技法と解脱という概念に関する科学的解析
2 注意と知覚に関する研究視点からヴィパッサナー瞑想を解析する
3 スピリチュアルケアと世代間伝達
おわりに
研究報告:実践と検証への手探り 井上ウィマラ(高野山大学文学部教授/スピリチュアルケア学・仏教瞑想研究)
はじめに
1 脳波測定のパイロットスタディから
2 エプスタイン氏との対話から
3 精神科診療における陪席調査から見えてきたもの
おわりに
第2部 心のはたらきと身心変容
- 1-1 マーラの分離・固体化理論
- 1-2 スターンの自己感の発達
- 1-3 響きあう場で働く心
- 1-4 抑うつ的態勢と思いやりの起源
- 1-5 愛着理論:概略
- 1-6 愛着理論:人生を俯瞰するケアの視点へ
- 2-1 悲嘆理論の基礎としての「悲哀とメランコリー」
- 2-2 死の変容の五段階説の背景
- 2-3 バリデーションというケア
第5章 響きあう他者と身心変容
心理療法と身心変容 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授/臨床心理学・ユング研究)
1 心身症の人格構造
2 心身症の心理療法
3 心理療法と身体の変容
4 身体による心理療法・訓練
心理療法の効果と身心の変容 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授/臨床心理学・ユング研究) 長谷川千紘(島根大学人間科学部講師/臨床心理学)
1 心理療法の効果
2 医学・経済モデルの浸透と認知行動療法
3 心理療法と身体の変容
4 身体の治療とこころの変容
5 こころの治療と身体の変容
インターフェイスとしての夢と身体・他者 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授/臨床心理学・ユング研究)
1 オープンシステムとしてのこころ
2 クローズドシステムとしてのこころ
3 インターフェイスとしてのイマジネーション
4 インターフェイスの危険と禁止
5 インターフェイスと死
6 インターフェイスと身体・他者
身心分離とインターフェイスにおける身心変容技法 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授/臨床心理学・ユング研究)
1 近代の心理療法と身心関係
2 心身症・身体疾患の心理学
3 心理療法と身体の変容
4 インターフェイスにおける身心変容
研究ノート:身体に住み込む、身体から旅立つ 井上ウィマラ(高野山大学文学部教授/スピリチュアルケア学・仏教瞑想研究))
1 身体に住み込む道のり
2 身体から旅立つ道のり
まとめ
第6章 瞑想と連関する身体技法 棚次正和(京都府立医科大学名誉教授/宗教哲学・祈り研究)
応用キネシオロジーの世界-O-リングテストは疑似科学か
はじめに
1 応用キネシオロジーの誕生とその評価
2 バイ・ディジタル・O-リングテストとはいかなるものか
3 バイ・ディジタル・O-リングテストに関する理論的説明
4 心理や霊性へのO-リングテストの応用
5 むすびに代えて
※補遺-O-リングテストの具体的な方法
倍音声明の音構造 加藤雅裕(関東学院大学非常勤講師/音響学) 安本義正(京都文教短期大学教授・学長/応用物理学) 永沢哲(京都文教大学准教授/宗教学(チベット仏教))
はじめに
材料および方法
結果
考察
まとめ
第7章 シンポジウム-身心変容の比較宗教学
平成23年度第2回身心変容技法研究会一般公開シンポジウム 身心変容技法の比較宗教学-心と体とモノをつなぐ技の総合的研究 内田樹(神戸女学院大学名誉教授・凱風館館長) 町田宗鳳(広島大学大学院総合科学研究科教授(当時)/(現)同大学名誉教授・「ありがとう寺」住職 齋木潤(京都大学大学院人間・環境学研究科教授/認知科学) 棚次正和(京都府立医科大学大学院医学研究科教授(当時)/(現)同大学名誉教授/宗教哲学・祈り研究) 鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授(当時)/(現)同大学名誉教授)
趣旨説明 鎌田東二
講演1 身心変容技法としての武道と芸道-合気道と能を中心に 内田樹
講演2 禅と念仏の身心変容技法 町田宗鳳
指定討論1 暴走による整理 齋木潤
指定討論2 身心変容と身体感覚 棚次正和
ディスカッション
質問とコメント
執筆者プロフィール
- この商品のレビュー ★★★★☆ (1)
- この商品のレビュー ★★★★☆
-
-
2018/02/26 身心脱落さん ★★★★☆
シンポジウムの記録が秀逸瞑想を科学する試みがていねいに記されている。身心変容技法シリーズの第一弾が瞑想である点が、興味深い。
本書は、内容的にはかなり専門的であり、何度かその厚さと難解さに挫折しそうになった。心と体とモノをつなぐワザについて、多角的な研究成果を発表している、最終章のシンポジウムは読みやすく、ディスカッションや質問も楽しめる、秀逸な記録。
-